ここから本文です
第九期介護保険料(第1号被保険者)について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年4月1日
介護保険制度は、各市区町村において3年ごとに事業計画を見直し、介護サービスの利用量(給付費)等に基づき、第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料を定めることとなっています。
三鷹市では、令和6年3月に「三鷹市高齢者計画・第九期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)」を策定し、令和6年度から令和8年度までの第九期介護保険料の基準額を月額6,300円(年額75,600円)に決定しました。
第九期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料
1 介護保険の財源
介護保険の給付にかかる費用のうち、50%は国・東京都・三鷹市の公費で、残りの50%を被保険者が納める介護保険料で賄っており、このうちの23%が第1号被保険者の介護保険料負担分となります。
2 第九期介護保険事業計画における保険料設定の背景
高齢化社会の進展に伴う介護を必要とするかたの増加、介護報酬の改定(3年間平均1.54%増)などの影響により、第九期(3年間)の総給付費は、第八期の約420億円(見込み額)から約450億円に増加が見込まれます。
3 介護保険料の上昇抑制対策
介護給付費準備基金の活用
介護保険保険給付費準備基金約5億7千万円を活用し、保険料の上昇を抑制しました。
低所得者への保険料軽減
低所得のかたへの対応として第1段階~第3段階のかたについては、公費投入による介護保険料軽減を引き続き行います。
なお、市独自の介護保険料個別軽減についても継続して実施します。
4 第九期の介護保険料の所得段階
第九期(令和6年度~令和8年度)では、介護保険法施行規則の改正に伴い、介護保険料の算定に係る基準所得額を改正しました。あわせて、所得段階を17段階から19段階に細分化しました。
5 介護保険料の仕組み
介護保険制度は、40歳以上のかたに納めていただく介護保険料と公費を財源に運営しています。介護保険料は65歳以上のかたと、40歳以上65歳未満のかたでは計算方法と納め方が違います。
基準額の算定方法
基準額(月額)=「居住している市区町村の介護サービスに必要な3年間の介護給付費見込額」×「65歳以上のかたの負担分(23%)」÷「その市町村の65歳以上のかたの総数」
全員一律で同じ介護保険料にしてしまうと、収入によっては負担が大きくなってしまうため、所得基準を段階に分けて、それぞれの保険料率を掛け合わせて金額を決める定額保険料となっています。
6 65歳以上のかた(第1号被保険者)
65歳以上のかたの介護保険料については、表1のとおりです。
基準額(第5段階)は、月額6,300円。表1の介護保険料は各段階とも年額(12カ月分)で示しています。100円未満は調整済みです。
| 所得段階 | 対象者 | 年額保険料 (基準額に対する割合) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者のかた 老齢福祉年金受給のかた(注1) 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が80万9,000円(令和6年度は80万円(注4))以下のかた |
20,400円 (基準額×0.270) |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計が80万9,000円(令和6年度は80万円(注4))超120万円以下のかた | 28,800円 (基準額×0.381) |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超のかた | 49,200円 (基準額×0.651) |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる場合で、本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計が80万9,000円(令和6年度は80万円(注4))以下のかた | 63,600円 (基準額×0.842) |
| 第5段階 | 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる場合で、本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計が80万9,000円(令和6年度は80万円(注4))超のかた | 75,600円 (基準額×1.000) |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた | 85,800円 (基準額×1.135) |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた | 96,000円 (基準額×1.270) |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた | 110,400円 (基準額×1.461) |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた | 128,400円 (基準額×1.699) |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた | 144,000円 (基準額×1.905) |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた | 158,400円 (基準額×2.096) |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた | 174,600円 (基準額×2.310) |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満のかた | 187,200円 (基準額×2.477) |
| 第14段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満のかた | 213,600円 (基準額×2.826) |
| 第15段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満のかた | 235,200円 (基準額×3.112) |
| 第16段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満のかた | 258,000円 (基準額×3.413) |
| 第17段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満のかた | 271,800円 (基準額×3.596) |
| 第18段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が3,000万円以上5,000万円未満のかた | 284,400円 (基準額×3.762) |
| 第19段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が5,000万円以上のかた | 294,000円 (基準額×3.889) |
- 注1 老齢福祉年金
- 明治44年4月1日以前に生まれたかたなどが対象となる福祉年金です。
- 注2 年金収入額
- 課税対象となる老齢(退職)年金のことで、遺族年金・障害年金などの非課税年金は除きます。
- 注3 合計所得金額
- 収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した金額です。基礎控除・扶養控除・医療費控除などの所得控除をする前の金額で、住民税などを算定する課税標準額とは異なります。長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除(控除後の額が0円を下回る場合は0円とする)した額を用います。
- なお、損失の繰越控除(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など)を受けている場合は、その適用前の金額です。
※本人が住民税非課税(第1段階~第5段階)の場合は、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除し、「給与所得」を含む場合は10万円を控除(「所得金額調整控除」の適用がある場合は、その控除前の額から10万円を控除)した額を用います。 - 注4 80万円
- 令和7年4月1日施行の介護保険施行令改正により、第1段階、第2段階、第4段階及び第5段階の基準として用いられている年金収入等の金額が80万円から80万9,000円に見直されました。なお、令和6年度の保険料を遡及して算定する場合は、見直し前の80万円が適用されます。
7 40歳から64歳までの医療保険に加入しているかた(第2号被保険者)
国民健康保険に加入しているかた
保険料の決まり方
国民健康保険の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。保険料は、第2号被保険者の前年の所得に基づいて計算される所得割と第2号被保険者の人数に応じて決まる均等割の合計になります。
詳細は「国民健康保険税」のページをご覧ください。
保険料の納め方
「医療分・後期高齢者支援金等分・介護分」をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入しているかた
保険料の決まり方
加入している健康保険ごとに設定されている介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。
保険料の納め方
職場の医療保険料と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9277
ファクス:0422-29-9820

 シェア
シェア ポスト
ポスト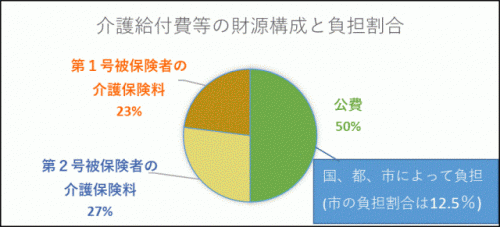
 防災関連情報
防災関連情報 休日・夜間診療
休日・夜間診療