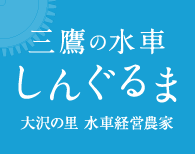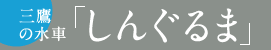大沢の里 水車経営農家の概要
 武蔵野地域の水車は、江戸期以降新田開発に伴って数多く設置され、明治末期から大正期にかけて産業技術近代化の中で最盛期を迎えました。その後昭和に入ると急激に減少していきましたが、その中で、峯岸家は文化14(1817)年以来、5代にわたり水車経営に携わってきました。
武蔵野地域の水車は、江戸期以降新田開発に伴って数多く設置され、明治末期から大正期にかけて産業技術近代化の中で最盛期を迎えました。その後昭和に入ると急激に減少していきましたが、その中で、峯岸家は文化14(1817)年以来、5代にわたり水車経営に携わってきました。
「新車(しんぐるま)」と呼ばれる峯岸家の水車は、文化5(1808)年頃創設され、その後度重なる改造を加え、現存する装置は、搗き臼(つきうす)14個、杵(きね)14本、挽き臼2台、やっこ篩(ふるい)2台、せり上げ2台を備えた多機能性を持つ両袖型の大型水車で、規模・形式ともに武蔵野地域を代表する営業用水車です。
野川の河川改修工事により昭和43(1968)年頃に水車の稼働は停止しましたが、ここには、水車とともに、母屋・カッテ・土蔵・物置などの建物や水車用用水路跡、「さぶた」なども現存しており、武蔵野地域の水車経営農家の旧態を留める貴重な民俗資料です。
ここは、現在、三鷹市によって管理・公開されています。
指定の足跡など
- 平成6(1994)年度
- 古民家(母屋)復元修理
- 平成6年4月
- 水車・古民家が峯岸清氏から三鷹市に寄贈される。
- 平成6年7月
- 三鷹市文化財指定 有形文化財「古民家(峯岸清氏旧宅)」
- 平成10(1998)年3月
- 東京都文化財指定 有形民俗文化財「武蔵野(野川流域)の水車経営農家」
[内容]- 敷地
- 構造物/母屋/カッテ/土蔵/物置/水車装置/水車用用水路跡/さぶた・排水口跡/通水橋
- 「付(つけたり)」の水車関係記録
- 平成11〜13(1999〜2001)年度
- 土蔵・物置修理工事
- 平成15(2003)年3月
- 屋敷地を三鷹市が購入する
土蔵・物置・カッテが峯岸清氏から三鷹市に寄贈される。 - 平成17(2005)年度
- カッテ修理工事
- 平成20(2008)年度
- 母屋修理工事
- 平成21(2009)年度
- 水車稼働整備工事
- 平成21年8月
- 日本機械学会 機械遺産認定「旧峯岸水車場」
- 平成22(2010)年度
- 「武蔵野(野川流域)の水車経営農家」から「大沢の里水車経営農家」に名称変更
水車を稼働した公開を開始する
「武蔵野(野川流域)の水車経営農家」(東京都有形民俗文化財)指定内容一覧
屋敷地
三鷹市大沢6丁目617-1の一部 宅地 55.04平方メートル
三鷹市大沢6丁目617-6の一部 宅地 969.04平方メートル
屋敷地総面積1.024.08平方メートル
構造物
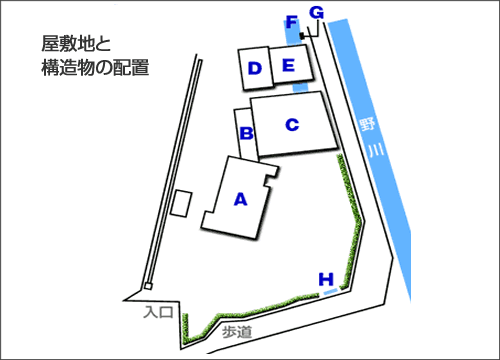
 A 母屋
A 母屋
文化10(1813)年代頃(伝承)。規模は、桁行7間、梁間3間。屋根は寄棟造、茅葺。4間取りで建築面積は75平方メートル。
B カッテ
建築年代は大正末年。規模は桁行7.85メートル、梁間2.77メートル。屋根はトタン葺。母屋の付設建物。
 C 水車装置
C 水車装置
文化5(1808)年頃創設。大正8(1919)年に大改造されています。水輪の直径約4.6メートル。幅約0.97メートル。詳しくは、「水車のしくみ」を参照してください。
 D 土蔵
D 土蔵
建築年代は明治14(1881)年。規模は桁行5.4メートル。梁間3.6メートル。屋根は、平成11〜13(1999〜2001)年度の補修工事により、茅葺き型屋根に復原し銅版葺きとしました。面積は、19.44平方メートル。
 E 物置
E 物置
土蔵に付属している建物。建築年代は、大正末(伝承)頃。建築面積は、24.3平方メートル。屋根は、平成11〜13(1999〜2001)年度の補修工事により、杉皮葺き型銅版葺きにしました。
 F 水車用用水路跡
F 水車用用水路跡
幅約1.5メートル。深さ約0.8メートル。長さ約10メートル。
 G さぶた・排水口跡
G さぶた・排水口跡
幅約1.4メートル
 H 通水橋
H 通水橋
野川から水田に水車用用水路(暗渠部分)をまたいで通水していましたが、その水車用用水路の上に掛かっていた石造の水橋。欄干の片側のみが現存しています。